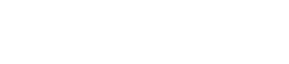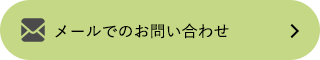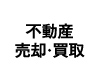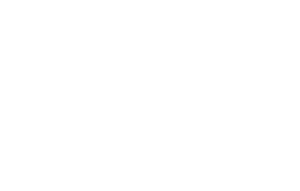
家はどこにでも建てられるわけじゃない!? ― 知っておきたい「建てられない土地」の話。|愛京住宅総合サイト
- 愛京住宅コーポレートサイトTOP
- 家づくりコラム
- 家はどこにでも建てられるわけじゃない!? ― 知っておきたい「建てられない土地」の話。

「気に入った土地を見つけたから、ここに家を建てよう!」
そう思った時、実はその土地が「家を建てられない場所」だった…というケース、意外とあるんです。
土地はすべて、都市計画法や建築基準法などのルールの中で分類されており、「家を建ててもいい場所」と「原則建ててはいけない場所」がはっきりと分かれています。今回は、そんな“家を建てられない土地”について、代表的なパターンをご紹介します。
家を建てられない場所とは?

最も有名なのがこの「市街化調整区域」。
これは都市の無秩序な拡大を防ぐために設けられた区域で、原則として新しく家を建てることができません。
農地や山林など、自然を残すエリアとして指定されていることが多く、開発行為そのものが制限されます。また、暮らしに必要不可欠なインフラ関係などが整備されていない場合も多いです。
ただし、過去に住宅が建っていた実績がある「既存宅地」や、農家の住宅として建てる場合など、条件を満たせば許可が下りることもあります。
2.建築基準法上の接道義務を満たさない土地
建築基準法第43条の接道義務により、幅員4m以上の道路に2m以上接していないと原則として建物を建築することができません。
接道義務が定められている理由としては、
・緊急車両の通行道路を確保するため
・災害時の避難経路を確保するため
・無秩序な開発を行わないため
などがあげられます。特に古い住宅街や路地奥の土地では要注意。
いざ建て替えようとしたら建てられなかった…なんてこともあるので、事前の確認が大切です。
すでに建物ある状態で接道義務を果たさない場所は、売買物件の対象になりえますが、「再建築不可物件」として取り扱われます。
3.農地法で保護されている農地
土地の用途を表す表記として、地目という項目があります。
この地目が「農地」のままでは、家は建てられません。
農地法によって守られており、勝手に宅地にすることはできないのです。
また、国立公園や自然公園内など、自然を保護するための特別地域でも、建築が厳しく制限されている場所があります。
建築不可とまではいかないが制限のかかる可能性があるもの

1.風致地区・景観地区などの制限区域
風致地区や景観地区に指定されている区域は、その景観を守るために建築の際に様々な制限が存在します。
周囲の環境に十分配慮して建築を行う必要があり、代表例でいうと岡山県倉敷市などがこれに該当します。景観地区で建物を建てる際の具体的な内容は、建物のも高さや色彩が決められているといったことになります。全く建築ができないわけではありませんが、建築に関する制限は必要以上にかかってしまうことを理解しておく必要があるでしょう。
2.文化財保護法による保護区域
文化財保護法に指定されている場所は、その土地に文化財が埋まっている可能性がある区域を指します。この区域で、建築工事をおこなう場合は、事前に文化財が埋蔵されているかの調査依頼を行政に申請する必要があり、その調査費用は土地の所有者の負担になります。もしその調査で文化財が見つかれば、国の文化財となるため、工期が大幅に遅れたり、建築に制限が発生する可能性があります。
建てられるかどうかを調べるには?
-

家は人生最大の買い物とも言われますが、「どこに建てるか」はその成功のカギ。
「安いから」「静かで景色がいいから」だけで土地を決めてしまうと、後で建築不可とわかって後悔することにもなりかねません。知らなかったでは済まされない土地選びだからこそ、購入前には、必ず市区町村の建築指導課や不動産業者に「この土地は住宅を建てられるのか」を確認しましょう。
検討している場所が上記に当てはまるかどうかは、以下4項目で調べることができます。
1.市区町村の建築指導課に確認するのが最も確実です。 -
2.登記簿・地目:宅地か農地かなど確認ができます。
-
3.都市計画図:用途地域、調整区域の確認ができます。
まとめ
「家は土地さえあれば建てられる」――そんな考えは要注意。
市街化調整区域、接道義務、農地法、災害リスクなど、さまざまな制限によって建てられないケースが意外と多く存在します。
土地選びは「安い」「広い」だけではなく、「建てられるか」「安全か」もセットで考えるのが賢い家づくりの第一歩です。